決算カードについての財政用語の解説
歳入
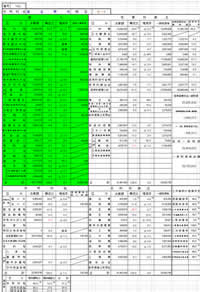
地方税
地方税法や市税条例の定めによって、徴収する租税です。市民のみなさんや市内に事務所を持つ法人等に納めていただくもので、歳入の根幹となるものです。
地方譲与税
国税として国が徴収したのち、一定の基準に従って地方公共団体に譲与される税です。市町村道の延長や面積に応じて譲与される地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税などがあります。
利子割交付金
預貯金や公社債などの利子所得に対するもので、徴収された県税のうち、一部が市町村の個人県民税額割合で交付されます。
配当割交付金
上場株式等の配当等に対するもので、源泉徴収された県税のうち、一部が市町村の個人県民税額割合で交付されます。
株式譲渡所得割交付金
上場株式等の譲渡益に対するもので、源泉徴収された県税のうち、一部が市町村の個人県民税額割合で交付されます。
地方消費税交付金
消費税10%のうち2.2%は地方のための消費税です。その消費税が人口などに応じて市町村に交付されるものです。
ゴルフ場利用税交付金
県がゴルフ場の利用行為に対して課する普通税であり、県が収納したゴルフ場利用税の7/10相当額を当該ゴルフ場所在の市町村に交付されるものです。(習志野市にはゴルフ場がないため、交付されていません)
特別地方消費税交付金
飲食店、旅館等にかかる県税である特別地方消費税の2分の1に相当する額を飲食店等の所在市町村に交付されていました。(平成12年3月末で廃止されています。)
自動車取得税交付金
自動車の取得に対して課される県税のうち一部を、市町村の道路の延長や面積に応じて交付されるものです。(R1年9月末で廃止されています。)
自動車税環境性能割交付金
自動車の燃費性能等に応じて、自動車の取得に対して課される県税のうち一部を、市町村の道路の延長や面積に応じて交付されるものです。
法人事業税交付金
資本金や所得等に応じて、事業を行う法人に対して課される県税のうち一部を、従業者数に応じて市町村に交付されるものです。
地方特例交付金
恒久的な減税の実施に伴う地方税の減収の一部を補てんするために創設されたものです。住宅借入金等税額控除による個人住民税の減収分や自動車税及び軽自動車税における環境性能割減収分などに対して交付されています。
地方交付税
国税の一部を、国が地方公共団体に交付する税のことです。地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡を図り、地方行政の計画的な運営を保障します。地方交付税には、普通交付税、災害など特別の事情に応じて交付される特別交付税があります。総額の94%が普通交付税として、6%が特別交付税として交付されます。普通交付税は、原則として基準財政需要額に対する基準財政収入額の不足額が交付されます。
また、平成23年度からは東日本大震災からの復旧・復興事業等に対して交付される震災復興特別交付税が上記2つの交付税とは別枠で措置されております。
交通安全対策特別交付金
交通違反の反則金を財源として、県から交通事故件数に応じて市町村に交付されるものです。
分担金・負担金
放課後児童会の育成料や養護老人ホームの入所料など、市が実施する事業により、利益を受ける方から、その受益を限度として徴収するものです。
使用料
体育館や谷津干潟自然観察センターなど、市の施設などを利用される方から徴収するものです。
手数料
住民票や戸籍など市の特定の行政サービスを受ける方から徴収するものです。使用料・手数料ともに受益者負担の考え方によるものです。
国庫支出金
国と市の経費の負担区分に基づいて、国が市に対して支出するものです。生活保護や児童手当(子ども手当)、児童扶養手当などの経費に対する負担金や、道路や学校の建設費に対する補助金等があります。
県支出金
県が市に対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するものと、県が国庫支出金を経費の全部または一部として交付するもの(間接補助金)があります。
財産収入
市有地の貸付料など市の財産活用についての収入や、市有財産の処分によって得た収入です。
寄附金
民法上の贈与で、金銭に限られるものです。使い道が特定されない一般寄附金と、使い道を限定した指定寄附金があります。
繰入金
普通会計、公営事業会計及び基金等の会計間における現金の移動のことです。例えば、普通会計の歳出に対し歳入が不足する場合に、基金を取り崩して普通会計に繰り入れ、不足額を補うことがあります。
地方債
地方自治体が「地方債」を発行し、国や、市内の銀行からお金を借りることです。また、平成15年度からは「はばたき債」として、市民のみなさんからもお金を借りていましたが、令和2年度から発行を休止しています。
臨時財政対策債
地方一般財源の不足に対処するため、通常地方債の発行が認められる投資的経費以外の経費にも充てることができる特例的な地方債。本来地方交付税で措置されるべきものです。
一般財源
地方自治体が自由に使えるお金のことです。地方税、地方譲与税、地方交付税などです。
特定財源
一般財源に対し、はじめからお金の使い道が決まっているものを特定財源といいます。地方債や、国庫支出金、都道府県支出金が、特定財源の代表的なものです(一部、一般財源もあります。)。
歳出
歳出は「性質別歳出」と「目的別歳出」に大きく分かれます。「性質別歳出」は、支出の「性質」で区分します。経費を横断的に経済的性質や効果で分析する方法です。「目的別歳出」は、支出の「目的」で区分します。市役所の機構別に近い区分になっており、個々の行政サービスの水準や行政上の特色を分類するのに有効です。
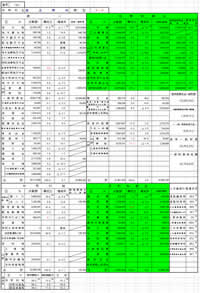
性質別歳出
人件費
市長・議員の報酬、職員の給与や退職金、各種審議会の委員報酬などです。
扶助費
社会保障制度の一環として、市が法令などに基づいて実施する給付費です。主に生活保護費や児童手当(子ども手当)などです。
公債費
市が発行した地方債の元利償還金(元金と利子)として支払う経費などをいいます。
物件費
人件費に計上されない賃金、旅費、交際費、消耗品や備品購入費、委託料などです。
維持補修費
道路、公共施設などを維持補修するためのものです。
補助費等
市から他の地方公共団体や民間の各種団体に対して、公益上必要な場合に支出される負担金や補助金です。
繰出金
普通会計、公営事業会計との間で、相互に支出される経費のことです。例えば、国民健康保険、介護保険の医療費や給付費などの経費や、雨水の処理などの下水道処理経費など公営事業会計の歳出に対し歳入が不足する場合に、普通会計から繰り出すことなどをいいます。
普通建設事業費
道路や公園、学校や公民館などの施設の建設に要する投資的経費をいいます。
目的別歳出
議会費
議会の仕事をする人の人件費や、議会運営のための費用です。
総務費
市役所や財産の維持管理、戸籍の管理や、税金の徴収などの費用です。
民生費
障害者や高齢者に対する福祉の充実、子育て支援などの費用です。
衛生費
環境保全、疾病予防、健康増進などの費用です。
労働費
失業対策、雇用対策などの費用です。
農林水産業費
農業の振興を図るための費用です。
商工費
商工業の振興や観光などの行政にかかる費用です。
土木費
道路や河川、公園など社会基盤の整備のための費用です。
消防費
消防などの災害対策や、防災などの安全対策のための費用です。
教育費
学校教育・生涯学習の充実、文化・スポーツ振興などの費用です。
公債費
市が発行した地方債の元利償還金(元金と利子)として支払う経費などをいいます。
収支

差引
歳入総額から歳出総額を引いたもので、形式収支といいます。算定式は形式収支=歳入総額—歳出総額
翌年度へ繰越すべき財源
本年度予定されていた事業が、特別な事情によって翌年度以降にずれてしまったときに、その事業に充てるお金として繰り越す財源のことです。
実質収支
形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を控除したもので、実質的な剰余金です。この実質収支から、黒字・赤字がどのくらいあるかわかります。赤字にしてはいけないのはもちろんですが、黒字が多いからといってよいとは限りません。収支の見通しをきちんと立て、サービスを効率的に市民の皆さんに配分したかどうか、行政運営の良し悪しを判断する重要なポイントになります。算定式は
実質収支=形式収支—翌年度へ繰越すべき財源
単年度収支
実質収支には前年度以前からの黒字が累計されているため、当該年度だけの収支を把握しようとするものです。実質収支から前年度の実質収支を差引き、黒字になれば、新たな剰余が生じたといえます。この1年で黒字・赤字をどれだけ増やしたかということです。算定式は
単年度収支=当該年度の実質収支—前年度の実質収支
積立金
財政運営を計画的にするため、または将来のために財源に余裕があるときに積み立てるお金のことです。
繰上償還金
地方債を期限より前に繰り上げて返済したお金のことです。翌年度以降の利子の負担を軽くするため、収支の余裕を見ながら返済します。
積立金取り崩し額
収支不足を補うために取り崩した財政調整基金の額です。
実質単年度収支
積立金、繰上げ償還金は、支出として収支の黒字を減少させるものですが、翌年度以降の財政運営のためには貢献する黒字の要素です。一方積立金の取り崩しは、収入ではありますが将来の赤字の要素になります。このようなやりくりがなかったら、収支はどうなるかということを表したものです。算定式は
実質単年度収支=単年度収支+積立金+繰上げ償還金—積立金取り崩し額
財政調整基金
年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金のことです。財源に余裕がある場合に積み立て、収入が著しく減ったときや、一時的な支出が必要になったときなどに取り崩します。
国の目から見た習志野市の財政状況
国民のみなさんは、全国どの自治体でも、最低限の行政サービスを同じように受けることができるように保障されていなければなりません。そのため国は自治体の標準の収入と支出を比べることにより、収入が不足する自治体には、「地方交付税」を交付します。ここでは、地方交付税制度についての財政用語を解説します。

基準財政需要額
市が標準的な行政サービスを提供するために必要な経費の規模のことで、実際の支出とは異なります。人口や道路の面積など全国統一のルールにより算定されます。
基準財政収入額
標準的な状態において見込まれる市税などの収入額の75%と譲与税などの税外収入の75%(一部100%)の合算額のことです。実際の収入とは異なります。基準財政需要額とともに、普通交付税の算定に用いられます。
標準財政規模
市の標準的な状態における経常的な一般財源の規模のことです。算定式は
標準財政規模=標準的な状態において見込まれる市税+普通交付税+譲与税・交付金等+臨時財政対策債発行可能額
財政指標等

財政力指数
市の財政力を示す指数です。仕事にかかるお金(基準財政需要額)に対して、税金がどのくらい納められているか(基準財政収入額)の割合です。財政力指数が大きいほど財政力が強いと見ることができ、1を超える自治体には普通交付税が交付されません。千葉県内の不交付団体は、成田市、浦安市、袖ケ浦市などであり、習志野市もかつて平成元、2、3年度のバブル期と、平成5、6、7年度に不交付団体になりました。算定式は
財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額 ←過去3年間の平均
実質収支比率
実質収支の標準財政規模に対する割合のことです。良好な財政運営を行っているかどうか示します。実質収支が黒字の場合は正数、赤字の場合は負数となります。3%〜5%程度が望ましいとされています。算定式は
実質収支比率=実質収支÷標準財政規模
経常収支比率
財政構造の弾力性(柔軟性)を示します。市が市民のみなさんのニーズにすぐに対応できるかどうかを示し、この比率が低いほど自由に使えるお金が多いということです。家計でいうとエンゲル係数にあたります。多様化・複雑化する市民のみなさんのニーズに応えるには、財政構造に余裕があることが必要です。一般的に75%〜80%が適正とされています。算定式は
経常収支比率=経常経費充当一般財源等÷(経常一般財源等+減収補てん債特例分+臨時財政対策債)
経常一般財源
毎年入ってくる自由に使えるお金のことです。(例:目的税を除いた地方税、普通地方交付税)
経常経費充当一般財源
毎年度必ず支出しなければならないお金のことを経常経費といいます。この経常経費にあてる経常一般財源のことです。
借金の返済
学校、病院、文化会館などのように、市民のみなさんが長い間使うことになる施設を建設する場合、建設費をその年だけの市税で充てると、翌年以降の市民は利用しているのに、負担しなくてすんでしまう場合があり、ある意味で不公平が生じます。そこで行政は、地方債などの借金をして、その返済という形で将来の市民にも負担をしてもらうことにより、現在と将来の市民のみなさんの負担を調整します。しかし、あまり地方債に頼ると返済が多額になり、将来の市の財政を圧迫して、新しい事業ができなくなってしまいます。そのようなことがないように、市税などの収入に対する返済(公債費)の割合などに配慮し、将来を見た財政運営をする必要があります
公債費比率
地方債を借りたときに、毎年度元利償還金(元金と利子)として支払う経費を公債費といいます。公債費比率とは、公債費の一般財源に占める割合をいいます。財政構造の硬直性をみる尺度であり、10%以下が健全の目安と言われています。
(健全化判断比率の算定に伴い、平成22年度決算カードからは削除されています。実質公債費比率で同様の算定をしています。)
公債費比率・債務負担行為を含む比率
将来の市民の皆さんの実質的な借金の負担割合のことです。債務負担行為とは、単年度予算主義(予算はその年度内に、本来執行すべきものという考え方)の例外で、今年度に契約などは行いますが、その支払いを期間と限度額を定め、後年度数年にわたって行うことです。例えば、建設工事、土地購入などです。公債費比率に、債務負担行為についての償還費を含め、標準的な収入に対する割合を示したものです。
(健全化判断比率の算定に伴い、平成19年度決算カードからは削除されています。実質公債費比率で同様の算定をしています。)
公債費負担比率
本来自治体が自由に使えるはずの市税等が、現実にはどの程度借金の返済に充てられているかを示します。この比率が高いほど自由に使える財源の幅が狭まり、財政の弾力性が乏しいことになります。10%以内が健全の目安とされていますが、15%を超すと健全財政の黄信号、20%を超すと赤信号といわれています。算定式は
公債費負担比率=公債費充当一般財源÷一般財源総額
起債制限比率
考え方は公債費比率と同じです。過去3カ年度間の平均が20%以上になると一部の地方債の発行が制限されます。
(健全化判断比率の算定に伴い、平成19年度決算カードからは削除されています。実質公債費比率で同様の算定をしています。)
債務負担行為比率
考え方は公債費比率と同じです。債務負担行為の返済額の、標準的な収入(標準財政規模)に対する割合のことです。算定式は
債務負担行為比率=債務負担行為合計÷標準財政規模)
(健全化判断比率の算定に伴い、平成19年度決算カードからは削除されています。実質公債費比率で同様の算定をしています。)
積立金現在高
財政運営を計画的にしたり、財源に余裕があるときに積み立てるお金を地方自治法上基金といいます。基金の総額を積立金現在高といいます。
地方債現在高
普通会計の地方債の残高です。習志野市が、国や銀行から借り入れた年度末の残高です。
債務負担行為支出予定額
地方債と同じように、将来返済しなければならない債務負担行為の残高です。
将来債務比率
自治体の借金が将来にわたってどの程度の財政負担となるかを表します。150%以下が望ましいといわれています。算定式は、
将来債務比率=(地方債現在高+債務負担行為支出予定額)÷標準財政規模
(健全化判断比率の算定に伴い、平成19年度決算カードからは削除されています。将来負担比率で同様の算定をしています。)
実質赤字比率
実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。財政規模にもよりますが、11.25%を超えると早期健全化段階(黄色信号)となる可能性があります。
連結実質赤字比率
公営企業を含む全会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。財政規模にもよりますが、16.25%を超えると早期健全化段階(黄色信号)となる可能性があります。
実質公債費比率
元利償還金等の標準財政規模に対する比率です。3年平均で表します。25%を超えると早期健全化段階(黄色信号)となり、地方債の発行制限がかかります。
将来負担比率
将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。350%を超えると早期健全化段階(黄色信号)となります。
公営事業会計等の状況
市は「一般会計」の他にも様々な行政活動を行っています。ガス・水道などの公営企業や公共下水道事業や、国民健康保険、介護保険事業など、市が主体となって行っている会計を一覧にしたものが「公営事業会計等の状況」です。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは財政課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9224 ファックス:047-453-9313
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。



更新日:2022年09月29日